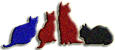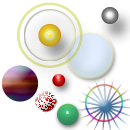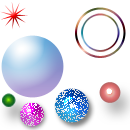我が家の猫集団 – 猫住(獣)民と常連達にまつわる話
猫屋敷になった経緯その1 - はじめの三匹
 今から十数年以上前、現在の家に移った頃は猫と暮らそうなどという大それた考えは微塵もなかった。と言うか、この国にそれほど長く居座るつもりは全く無かった。ところが、事もあろうに(!)この家には既に二匹もの猫がいた。一匹は Fred(フレッド)というかなり高齢のキジトラ、もう一匹は Reilly(ライリー)という名の片目を失くした黒猫。この二匹、一緒にすると必ず荒くれ者のライリー(雄)が臆病者のフレッド(雌)を虐めて始末が悪いので、ライリーは階下、フレッドは階上とそれぞれに別のスペースを与えトラブルを避けていたが、1998年の秋、一ヶ月かそこらの短い間に二匹とも逝ってしまった。
今から十数年以上前、現在の家に移った頃は猫と暮らそうなどという大それた考えは微塵もなかった。と言うか、この国にそれほど長く居座るつもりは全く無かった。ところが、事もあろうに(!)この家には既に二匹もの猫がいた。一匹は Fred(フレッド)というかなり高齢のキジトラ、もう一匹は Reilly(ライリー)という名の片目を失くした黒猫。この二匹、一緒にすると必ず荒くれ者のライリー(雄)が臆病者のフレッド(雌)を虐めて始末が悪いので、ライリーは階下、フレッドは階上とそれぞれに別のスペースを与えトラブルを避けていたが、1998年の秋、一ヶ月かそこらの短い間に二匹とも逝ってしまった。
片目のライリー
ライリーの名の由来は、アイルランドのバラッドReilly's Daughterの歌詞から。彼はもともと野良であったが、ある日マグパイ(カササギ)との熾烈な戦いの末に片目を潰され食物源である当家に尻尾を巻いて逃げ込んで来たとか。急遽動物病院に連れて行かれ、それ以来野良生活を半分あきらめ家の中に住みつき始めたドンくさい無鉄砲者であった。ライリーは半飼い猫になる前からエイズ・キャリアで、当家に入居後数年で発症しその後まもなく波乱万丈の短い生涯を終えた。運が悪いようで、実は果報者の猫だったと思う。
老婦人フレッド
7歳くらいの時に姉妹のジンジャーを癌で亡くしたが、当猫はその後十年以上も生き続けた 。18歳で旅立つ二、三週間前まで病気一つしなかったらしい。彼女は老齢の為か、とても温厚で人懐こい性格だった。人間と同じように布団から頭を出して枕に乗せ、小さないびきをかきながら寝ていた姿を思い出す。先に逝ったジンジャーと再会し、以前のように姉妹で踊ってるといいが。
それから八週間ほどたって、猫砂や餌がかなり残っているし家の中が寂しいから子猫でも飼おうかという話になり、同居人のTACと共に行きつけの獣医に赴いた。その獣医はアニマル・レスキューの団体に関わっており、新しい飼い主が現れるのを待っている子猫数匹の面倒を見ていると言う。そいつは願ったり叶ったりとばかりに獣舎をのぞくと、そこには生後二ヶ月から六ヶ月(一匹はどういう訳かもう成猫の大きさだったが)くらいまでの子猫が全部で8匹ほど収容されていた。たまたまその中に私好みのハチワレ、タキシード、白足袋、短毛の黒がちブチ猫を見つけ、即座に引き取りを決定。その猫は一匹だけ兄弟達の背後に隠れるようにして檻から出るのを嫌がったが、こちらはお構い無しにそいつを引きずり出しバスケットの中に押し込んだ。TACと「どうせ飼うならもう一匹」と意見が一致して、互いに何もかもそっくりなキジトラ三兄弟の中からさんざん迷った挙句一匹を選び、さあ、任務完了と思った矢先にスタッフの女性がほぼ成猫に近い一匹のキジトラ(雌)を売り込み始めた。(事実かどうか怪しいものだが)保護される前は老婦人の元で唯一の猫として飼われていたが、高齢か何かの理由で飼い主に見放されたとか。当の猫はまだ生後六ヶ月くらい(それにしてはやけにでかい)だがとてもおとなしく、予防接種も済んでいるのでもう一匹どうかと説得されTACは言われるがままに承諾してしまったのであった。数日後にその獣医で避妊手術を受ける事になったその成長し過ぎのキジトラを残して、3匹分の寄付金を納めた後ミャアミャア鳴く二匹のちっぽけなオス猫と共にそそくさと獣医を出たのは約14年前だった。
気難し屋Angie (アンジー)
 推定生年月日:1998年4月。2016年11月5日早朝(6時頃)没。ブッチ、ドゥーゴル(下記参照)と共にレスキュー団体から貰い受けたキジトラの雌猫。はじめAngelと名付けられたが、後にAngieと呼ばれるようになった。我が家に来た当初は静かで結構面倒見の良い若い猫だったが、半年、一年と経って他の二匹が成長するにつれ次第に彼らを毛嫌いするようになった。今でも頻繁にではないが、誰か(猫)が近付くだけでガミガミ言いながらパンチをくらわせたり、小走りに逃げ去ったりしている。彼女は単独で飼われる方が幸せなんだろう。飼い主以外の人間にはかなりビビるが、他の猫に対しては割と強気である。話しかけると目を細め眠ったふりをし、人の手のひらに自分の頭を押し付け撫でてもらいたがる。アンジーには妙な習癖があって、人間が階段の踊り場を通ると後を追って側に駆け寄り顔を見上げて何回かミャーーと鳴いたり、とりわけ夜中に物を転がしながら甲高い声でうるさく鳴いたりする。若い頃にはそんな行動は無かったが… 彼女は非常に健康な猫で、これまでのところ獣医のお世話になったのは我々が完全室内飼いを始める前、外猫に尻尾を噛まれて怪我をした時の一度だけである。この出来事と、ブッチの朝帰り、近所に野良猫が増え始めた事などをきっかけに我が家の猫達は軟禁される羽目になった。
推定生年月日:1998年4月。2016年11月5日早朝(6時頃)没。ブッチ、ドゥーゴル(下記参照)と共にレスキュー団体から貰い受けたキジトラの雌猫。はじめAngelと名付けられたが、後にAngieと呼ばれるようになった。我が家に来た当初は静かで結構面倒見の良い若い猫だったが、半年、一年と経って他の二匹が成長するにつれ次第に彼らを毛嫌いするようになった。今でも頻繁にではないが、誰か(猫)が近付くだけでガミガミ言いながらパンチをくらわせたり、小走りに逃げ去ったりしている。彼女は単独で飼われる方が幸せなんだろう。飼い主以外の人間にはかなりビビるが、他の猫に対しては割と強気である。話しかけると目を細め眠ったふりをし、人の手のひらに自分の頭を押し付け撫でてもらいたがる。アンジーには妙な習癖があって、人間が階段の踊り場を通ると後を追って側に駆け寄り顔を見上げて何回かミャーーと鳴いたり、とりわけ夜中に物を転がしながら甲高い声でうるさく鳴いたりする。若い頃にはそんな行動は無かったが… 彼女は非常に健康な猫で、これまでのところ獣医のお世話になったのは我々が完全室内飼いを始める前、外猫に尻尾を噛まれて怪我をした時の一度だけである。この出来事と、ブッチの朝帰り、近所に野良猫が増え始めた事などをきっかけに我が家の猫達は軟禁される羽目になった。
【追録】2016年10月半ばのある日、アンジーが食べ物をくわえるのに難儀している様子で一旦口に入れた物をボロボロこぼすという動作を繰り返していた。食欲はあるようだがこちらが目の前に好物を置いても自分から食べようとしない。試しにハムを細くちぎったものを鼻先に持っていくとアンジーはそれをするりと飲み込んだ。これはひょっとして虫歯にでも侵されて普通に食えないのだろうか。2~3ヶ月前から徐々に食が細くなり痩せてきたことには気づいていたがそれ以前にはすでにソファにさえ飛び乗れないほど足腰が弱っていたため(体重の減少は)高齢が原因だろうなどと思い込んでいた。その後数日間、一日に何回かアンジーだけを台所に引き入れ手から食べ物を与えてみたが、ある時はそこそこの量を食べまたある時はほんの一口食うか食わないかでそっぽを向き台所内をウロウロと歩き回るのだった。やっと都合がついて当猫を動物病院に連れて行ったところ虫歯だけではなく内臓や他の器官に病巣がありそうだから(その頃アンジーは水をやたら飲んでいた)血液検査と尿検査を行って診断、治療したいと言われ即座に採血。その場は薬の処方も受けず帰宅した。哀れにもアンジーの膀胱が空っぽであったため尿検査は出来なかったらしいが数時間後獣医は電話で血液検査の結果を知らせてきた。疑っていた腎臓障害の心配はないもののある種の腸疾患(癌腫?)を患っているようだ、生検で正確な診断が可能だが老猫にとっては負担が大きいため通常その方法は用いられない、残念ながら虫歯を取り除いて摂食を助長させることで数週間から1ヶ月の延命を期待するしかない、というのが獣医の言葉だった。その時点でアンジーの余命がどれくらいだったのか不明だが悲しいかな、我々は獣医の勧めに従うこと以外何も思いつかなかった。次の日再びアンジーを連れて動物病院へ。歯の治療前に痩せ細ったアンジーの体力を回復させる必要があったのでその晩は点滴のため入院となった。翌日の夕方、抜歯治療を終えたアンジーを迎えに行った際「彼女は麻酔から目覚めた後餌を貪り食った、メシの与え過ぎに注意」と獣医に聞かされたがその夜当猫は以前と同じく殆ど何も口にしなかったのだった(危険を冒して受けさせた歯の治療は何の役にも立たなかったのか…?)。しかし驚いたことに翌朝アンジーは餌をもりもり食い活発に動き回って我々をひと安心させた。以降数日間はその状態が続き、我々はアンジーを他の猫と別にして台所で彼女の好みそうなものを与えたり(食欲増進を兼ねて)陽のあたる裏庭を散歩させたりして出来る限り世話をしてやったのだが、ほどなくして再び当猫の食欲は減退し、こちらが台所の扉を開けると断りも無く中に駆け込むもののアンジーは何を口にする訳でもなくただ室内をのろのろと動き回ったり勝手口の扉の前でうつむいてじっと屋外の匂いを嗅いだりするのみであった。そのうち液体以外は摂取しなくなった当猫は思いのほか急速に衰えていった。
他界する二日前アンジーは鈍重ながらもあちこちへ移動し何度も大きな鳴き声を発した。また台所への扉に張り付く様子から恐らく裏庭に出たかったのだろうと思うがあいにく我々が帰宅した頃には外はもう真っ暗で気温も低かったため当猫を連れ出すことは出来なかった。
その翌日はすでに動く事もままならないほど弱りきっていたアンジーはほとんどの時間居間にある薪をくべたストーブの横にうずくまりじっと老骨を温めていた。午前中鶏がらスープをひと舐めふた舐めしただけで、もはや食うことへの興味を失ったようだった。可能なうちになるべく外の空気を味わわせたいと考え(気分転換のためにとでも言うべきか)昼過ぎに半ば無理やり当猫を連れて裏庭へ出てみたもののアンジーは芝の上にへたり込んだまま周りをぼんやり眺めるばかりで10分も経たないうちに屋内に入りたがったのだった。その夜アンジーは不意に身を起こしふらつきながら数歩進んではくずおれるという動作を何回か繰り返した(その都度筆者は絶命したかのように横たわる当猫を元の場所に戻さざるを得なかった)。多分、いよいよ虫の息となって彼女は本能的により安全で喧噪のない場所に避難しようとしたのではないかと想像する。
そして歯の治療から約2週間後の早朝、アンジーは静かに息を引き取った。(思った以上に早い別れとなった![]() ) 彼女は最後まで殆ど金も手間もかからない慎ましい/おとなしい猫だった。あまり長く苦しまなかったのがせめてもの救いである。
) 彼女は最後まで殆ど金も手間もかからない慎ましい/おとなしい猫だった。あまり長く苦しまなかったのがせめてもの救いである。
猫の中の猫Butch (ブッチ)
 推定生年月日:1998年10月。2008年10月没。アンジー(上記参照)、ドゥーゴル(下記参照)と共にレスキュー団体から貰い受けた黒がちの雄ブチ猫。ブッチの思い出は山ほどあるが、書けば書くだけ後悔の念が強くなるので、出来るだけかいつまんで話そうと思う。彼は私が理想とする猫の性質を殆ど全て持った異彩児モギーだった。ブッチを特別扱いする事が多かったので、同居人からは「恥も外聞もないえこひいきだ。」とよく言われていた。小さい頃は腕白小僧で、他の猫を追い回したり布団に頭や前足を突っ込んで人間の手足を攻撃したりして手に負えなかったが、成猫になってからは新入り猫(特にオス)の面倒をよく見、人間の膝や身体の上に乗っかって丸くなるのを好むようになった。(かと言って、人にベタベタする訳ではなかったが。) 一、二度、膝の上で屍さながらに完全脱力して眠りこけていた事があった。飼い主以外の人間は苦手だったが、我々のことなど屁とも思わず廊下や階段のド真ん中に超然と座って近付いても警告しても身動き一つしない図太い奴だった。外出させていた頃、用を足しにわざわざ家まで戻って来たり、木に止まった鳥を見てカッカッカッとやったり、雨降りの外を見て我々に抗議したりといろいろ楽しませてくれたものだ。自ら窓を開けてそこから脱走したり、ミーアキャットの様に前足を上げ首を伸ばして窓の外を凝視したりする事も何度かあった。ある日、様子がおかしいので獣医に連れて行ったところFIV陽性と診断された。その頃はもうとっくに内飼いを始めて(その5、6年前から)いたが、昼間短時間だけ出入りを許されていた最初の一年半ばかりの間に感染したのか、それとも生まれた時にはすでにキャリアだったのか知る由も無い。布団の中に隠れて丸二日ほど餌も水も拒否する事が何度かあったがブッチは診断後二年以上生き延び、調子の良い時は目の前に丸薬を置くだけでペロッと飲んだりと、比較的看護しやすい猫だった。2008年10月我々が休暇旅行で不在の為、獣医に預けられている間に(よりによって一番安全な筈の獣医で、それまで元気そうだったにもかかわらず)、我々には文句も別れも言わずこの世を去った。まさに痛恨の極みだった。彼の死因は不明である。あんな良い猫とはもう二度とめぐり会えないかもしれない。
推定生年月日:1998年10月。2008年10月没。アンジー(上記参照)、ドゥーゴル(下記参照)と共にレスキュー団体から貰い受けた黒がちの雄ブチ猫。ブッチの思い出は山ほどあるが、書けば書くだけ後悔の念が強くなるので、出来るだけかいつまんで話そうと思う。彼は私が理想とする猫の性質を殆ど全て持った異彩児モギーだった。ブッチを特別扱いする事が多かったので、同居人からは「恥も外聞もないえこひいきだ。」とよく言われていた。小さい頃は腕白小僧で、他の猫を追い回したり布団に頭や前足を突っ込んで人間の手足を攻撃したりして手に負えなかったが、成猫になってからは新入り猫(特にオス)の面倒をよく見、人間の膝や身体の上に乗っかって丸くなるのを好むようになった。(かと言って、人にベタベタする訳ではなかったが。) 一、二度、膝の上で屍さながらに完全脱力して眠りこけていた事があった。飼い主以外の人間は苦手だったが、我々のことなど屁とも思わず廊下や階段のド真ん中に超然と座って近付いても警告しても身動き一つしない図太い奴だった。外出させていた頃、用を足しにわざわざ家まで戻って来たり、木に止まった鳥を見てカッカッカッとやったり、雨降りの外を見て我々に抗議したりといろいろ楽しませてくれたものだ。自ら窓を開けてそこから脱走したり、ミーアキャットの様に前足を上げ首を伸ばして窓の外を凝視したりする事も何度かあった。ある日、様子がおかしいので獣医に連れて行ったところFIV陽性と診断された。その頃はもうとっくに内飼いを始めて(その5、6年前から)いたが、昼間短時間だけ出入りを許されていた最初の一年半ばかりの間に感染したのか、それとも生まれた時にはすでにキャリアだったのか知る由も無い。布団の中に隠れて丸二日ほど餌も水も拒否する事が何度かあったがブッチは診断後二年以上生き延び、調子の良い時は目の前に丸薬を置くだけでペロッと飲んだりと、比較的看護しやすい猫だった。2008年10月我々が休暇旅行で不在の為、獣医に預けられている間に(よりによって一番安全な筈の獣医で、それまで元気そうだったにもかかわらず)、我々には文句も別れも言わずこの世を去った。まさに痛恨の極みだった。彼の死因は不明である。あんな良い猫とはもう二度とめぐり会えないかもしれない。
無邪気な老いぼれDougal (ドゥーゴル)
 推定生年月日:1998年10月。2014年11月17日没。アンジー、ブッチ(上記参照)と共にレスキュー団体から貰い受けたキジトラの雄猫。飼い主が決めあぐねていた為、彼にはしばらく名前が無かったが、チャンネル4 (UK放送局)のテレビ番組「ファーザー・テッド」に出てくる子供並みの知能しかない神父にちなんでドゥーゴルと名付けられた。ドゥーゴル(猫)は、度々早食い・大食いをして所構わず吐きまくり、飼い主だろうと見知らぬ人間だろうとしつこく膝に乗って濡れた鼻を相手の顔に擦り付け、火のついた暖炉に近付き過ぎてひげや尻尾を焦がしても気付かず、叱られているのにおやつが貰えると思って目を輝かせる、とその名の通りボンクラで全く世話の焼ける奴である。おまけに彼は若い頃から病気がちで、肝臓だの膵臓だのを悪くして獣医を儲けさせている。その所為か痩せぎすで、我が家の猫の中では最も軽い。(シャム猫の血が混じっているらしいが賢さや気高さとはまるで無縁である。) のん気で温和な性質だが、突然走り出したり窓枠に飛び乗ってワーオ、ワーオと何度も遠吠えしたりする。夏場の週末リード付きで庭を散歩させる際、外猫が近寄って来て唸り声をあげ威嚇してもドゥーゴルは鼻をくんくんさせ何処吹く風である。肝が据わっていると言うか鈍感と言うか、周りで何が起ころうが我関せずとばかりに眠り呆けるのが得意。そのおかげで、アイブス(後に紹介)新加入のため他の猫達がピリピリしていた頃、一触即発の気配を感じ取れず小競り合いに巻き込まれて左目を負傷した。しばらく治療を施されたが結局眼球摘出の憂き目にあった。当猫は今でもノホホンとしている。
推定生年月日:1998年10月。2014年11月17日没。アンジー、ブッチ(上記参照)と共にレスキュー団体から貰い受けたキジトラの雄猫。飼い主が決めあぐねていた為、彼にはしばらく名前が無かったが、チャンネル4 (UK放送局)のテレビ番組「ファーザー・テッド」に出てくる子供並みの知能しかない神父にちなんでドゥーゴルと名付けられた。ドゥーゴル(猫)は、度々早食い・大食いをして所構わず吐きまくり、飼い主だろうと見知らぬ人間だろうとしつこく膝に乗って濡れた鼻を相手の顔に擦り付け、火のついた暖炉に近付き過ぎてひげや尻尾を焦がしても気付かず、叱られているのにおやつが貰えると思って目を輝かせる、とその名の通りボンクラで全く世話の焼ける奴である。おまけに彼は若い頃から病気がちで、肝臓だの膵臓だのを悪くして獣医を儲けさせている。その所為か痩せぎすで、我が家の猫の中では最も軽い。(シャム猫の血が混じっているらしいが賢さや気高さとはまるで無縁である。) のん気で温和な性質だが、突然走り出したり窓枠に飛び乗ってワーオ、ワーオと何度も遠吠えしたりする。夏場の週末リード付きで庭を散歩させる際、外猫が近寄って来て唸り声をあげ威嚇してもドゥーゴルは鼻をくんくんさせ何処吹く風である。肝が据わっていると言うか鈍感と言うか、周りで何が起ころうが我関せずとばかりに眠り呆けるのが得意。そのおかげで、アイブス(後に紹介)新加入のため他の猫達がピリピリしていた頃、一触即発の気配を感じ取れず小競り合いに巻き込まれて左目を負傷した。しばらく治療を施されたが結局眼球摘出の憂き目にあった。当猫は今でもノホホンとしている。
【追録】2014年9月上旬頃のある日、ドゥーゴルが口をもごもごさせ頭を揺さぶるや否や歯を一本吐き出した。何年か前に抜歯治療を受け、すでに半分以上の歯が失われている状態であったが更に何本か腐食しているらしかった。少量の出血もあったので数日後動物病院へ。再び(全身麻酔無しで)抜歯治療を施され残りの歯は片手で数えられるほどとなった。それから一ヶ月ほど経って彼は悪臭と共に口から白っぽい粘液を垂らし始めた。一日中膿のようなよだれと濁った血を大量に流しながらも食欲は全く衰えていない様子でいたって元気だったが、(諸事情により)何日か後に再度動物病院へ。獣医によると舌の下側にしこりが見られ細菌の感染かまたは口腔癌の可能性が高いという。生体検査を勧められたが老齢のうえ病弱なドゥーゴルには全身麻酔や手術に耐えられるだけの体力がないと判断し、抗生物質と痛み止めで対処することに。(この国にはまともな癌治療をする動物病院が少ない) その後白濁の粘液はぴたりと止まったものの出血は相変わらず続いていた。この時分だったか、ドゥーゴルは小さな子供がむずかるように「うーん、うーん」と小さなか細いうめきを絶えず発していた。(理由は不明) また、好物のドライフードにそっぽを向き(腫れ物によりウェットタイプの餌も食べづらいため)食事時間が次第に長くなっていったが、それでも当猫は餌をせがむ事をやめなかった。やがて食べる量が徐々に減り初回の鎮痛薬がなくなる頃(前回の通院から約2週間後)にはドゥーゴルの体重もすっかり減少していた。いよいよ先は長くないと覚悟し始めたが、それにしても当猫は未だにあちこち動き回り飯時になると餌場に飛んでくる。ふと思い至って茶さじを使いドゥーゴルにとろとろの餌を与えてみたところ、奴は調子に乗ってさじを飲み込まんばかりにガツガツ食ったのだった。それからしばらく生のステーキ肉や水分の多い高価なキャットフードなどは自力で食べ![]() ローストチキンのかけらや焼き魚(の身)などは文字通り我々の手を借りて口にし、一時は結構肉付きが良くなったドゥーゴルだったが11月の初め辺りから再び摂取量が減ってミルクや液状の食物だけで日をしのぐようになり、またもや段々と痩せ細っていった。口内の腫れ物は休み無く成長し下顎がひずみ当猫はもはや口を閉じることも出来ない。よだれや出血は以前と同じように続き、前足の被毛には常に血の塊がこびり付いていた。(その他の状態は書くに忍びない—猫というのは何と我慢強い生き物だろうか) そんな痛ましい姿でありながらドゥーゴルの食欲だけは健在だった。だが、彼の腹は肉や猫餌を要求しているのに食べるという行為ができない。(鎮痛薬など殆ど効いていなかったのだろう…我々の助けを嫌がることがたびたびあった) それは食うことが生きがいのドゥーゴルにとって過酷でまさに拷問のような日々だったに違いない。ある朝彼はとりわけ好んでいた特製の流動食さえ口にしなくなった。次の日、不本意ながら(成り行きがたやすく予想できたため)ドゥーゴルを動物病院に連れて行くと獣医は当猫を一目見るなり「これ以上生かしておくのは残忍すぎる」とひと言。彼女(獣医)は前回の診察の際すでに早期の安楽死以外選択肢はないと考えていたようだった。同感した訳ではないが、ドゥーゴルの生の質は低下するばかりで、我々にはこれ以上手の打ちようがない。どちらを選んでも悔いは残ると思いつつ、苦痛をもうしばらく長引かせるか、速やかに苦しみから解放してやるか、思い切るしかなかった。(安楽死用薬剤の前に)麻酔薬を投与されてから数分後ドゥーゴルは診察台にへたり込みピクピク体を震わせた。ただ”安楽”に逝ったことを願うばかりである。
ローストチキンのかけらや焼き魚(の身)などは文字通り我々の手を借りて口にし、一時は結構肉付きが良くなったドゥーゴルだったが11月の初め辺りから再び摂取量が減ってミルクや液状の食物だけで日をしのぐようになり、またもや段々と痩せ細っていった。口内の腫れ物は休み無く成長し下顎がひずみ当猫はもはや口を閉じることも出来ない。よだれや出血は以前と同じように続き、前足の被毛には常に血の塊がこびり付いていた。(その他の状態は書くに忍びない—猫というのは何と我慢強い生き物だろうか) そんな痛ましい姿でありながらドゥーゴルの食欲だけは健在だった。だが、彼の腹は肉や猫餌を要求しているのに食べるという行為ができない。(鎮痛薬など殆ど効いていなかったのだろう…我々の助けを嫌がることがたびたびあった) それは食うことが生きがいのドゥーゴルにとって過酷でまさに拷問のような日々だったに違いない。ある朝彼はとりわけ好んでいた特製の流動食さえ口にしなくなった。次の日、不本意ながら(成り行きがたやすく予想できたため)ドゥーゴルを動物病院に連れて行くと獣医は当猫を一目見るなり「これ以上生かしておくのは残忍すぎる」とひと言。彼女(獣医)は前回の診察の際すでに早期の安楽死以外選択肢はないと考えていたようだった。同感した訳ではないが、ドゥーゴルの生の質は低下するばかりで、我々にはこれ以上手の打ちようがない。どちらを選んでも悔いは残ると思いつつ、苦痛をもうしばらく長引かせるか、速やかに苦しみから解放してやるか、思い切るしかなかった。(安楽死用薬剤の前に)麻酔薬を投与されてから数分後ドゥーゴルは診察台にへたり込みピクピク体を震わせた。ただ”安楽”に逝ったことを願うばかりである。
<2014年11月 記>
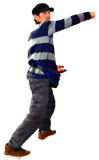

 セユアイのトリヴィア雑記?!ヨーロッパ辺境の英語圏で猫に囲まれラグビー観戦
セユアイのトリヴィア雑記?!ヨーロッパ辺境の英語圏で猫に囲まれラグビー観戦